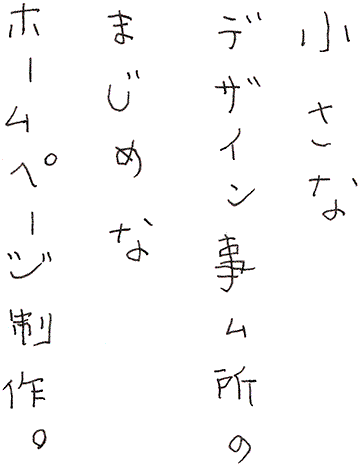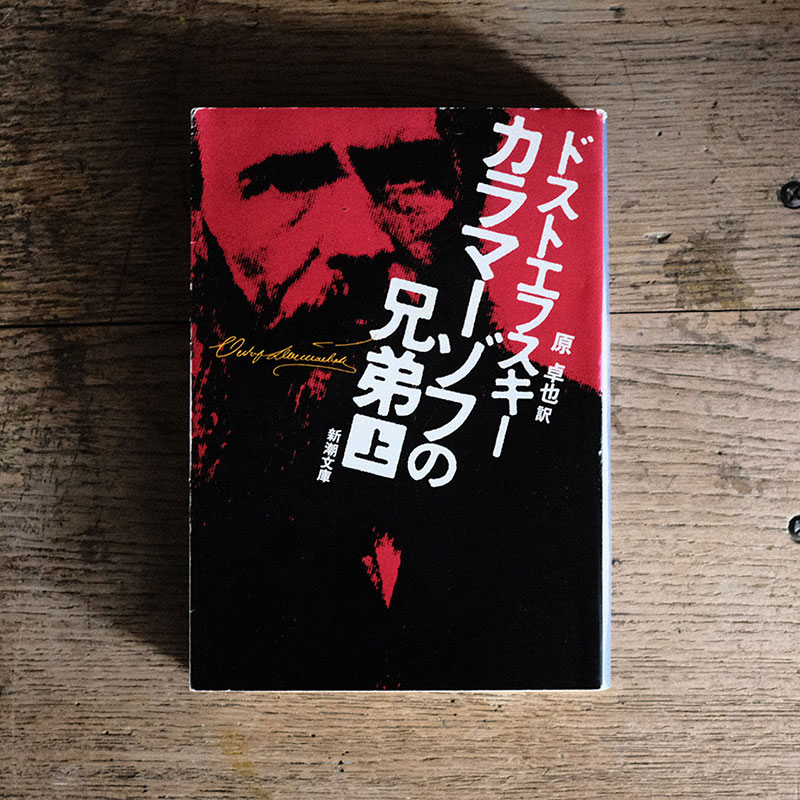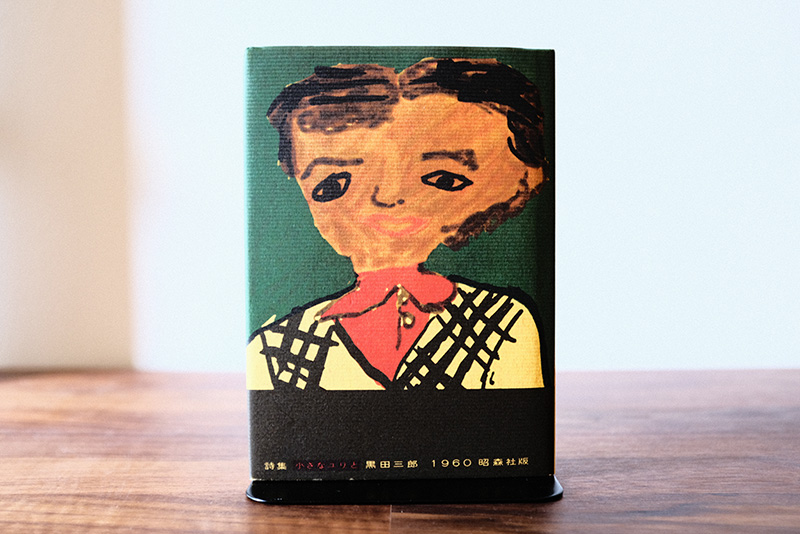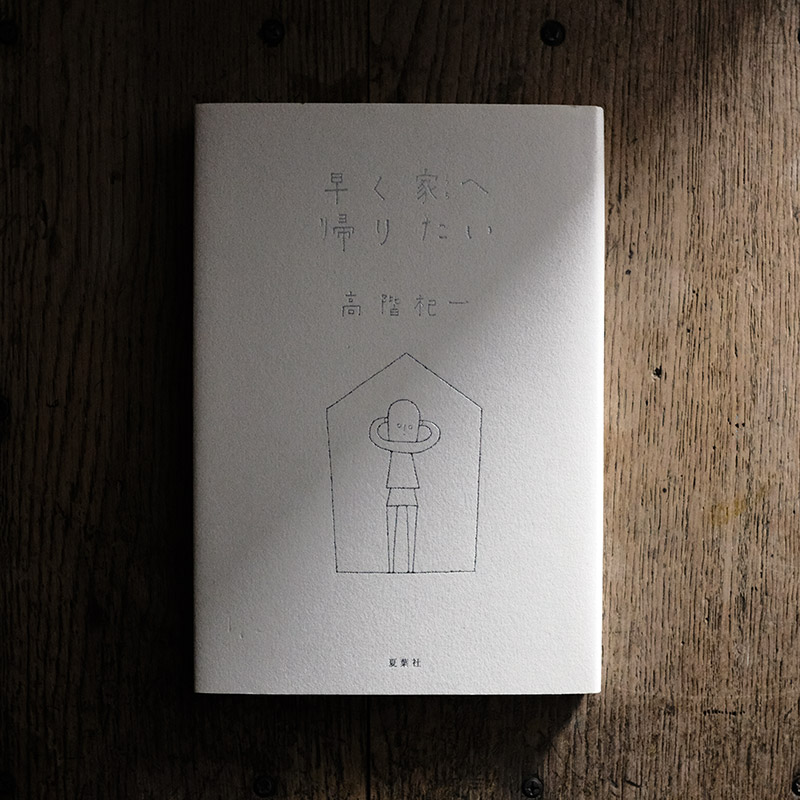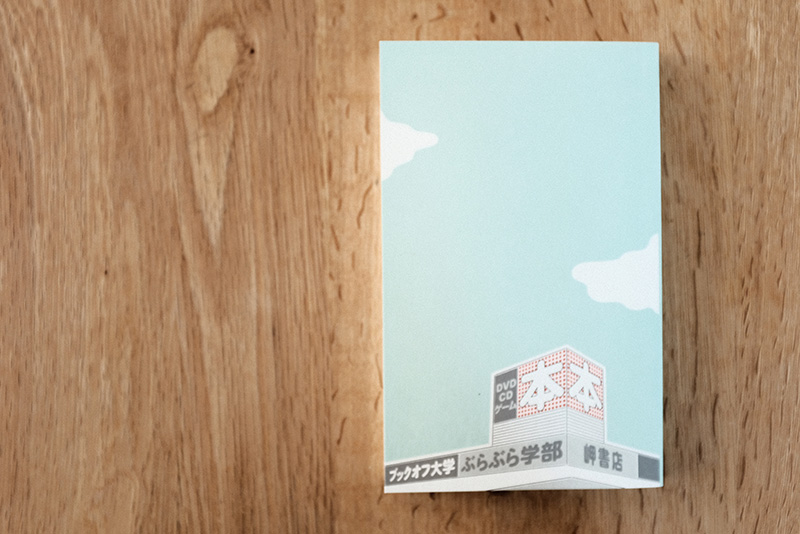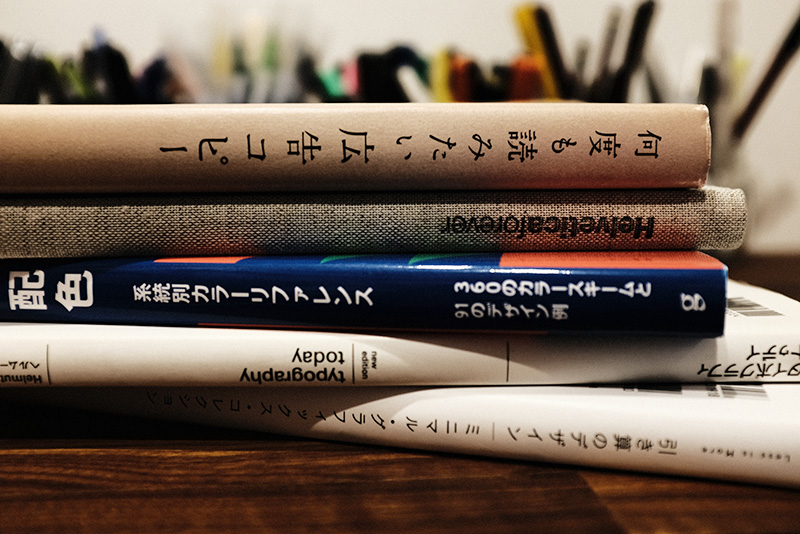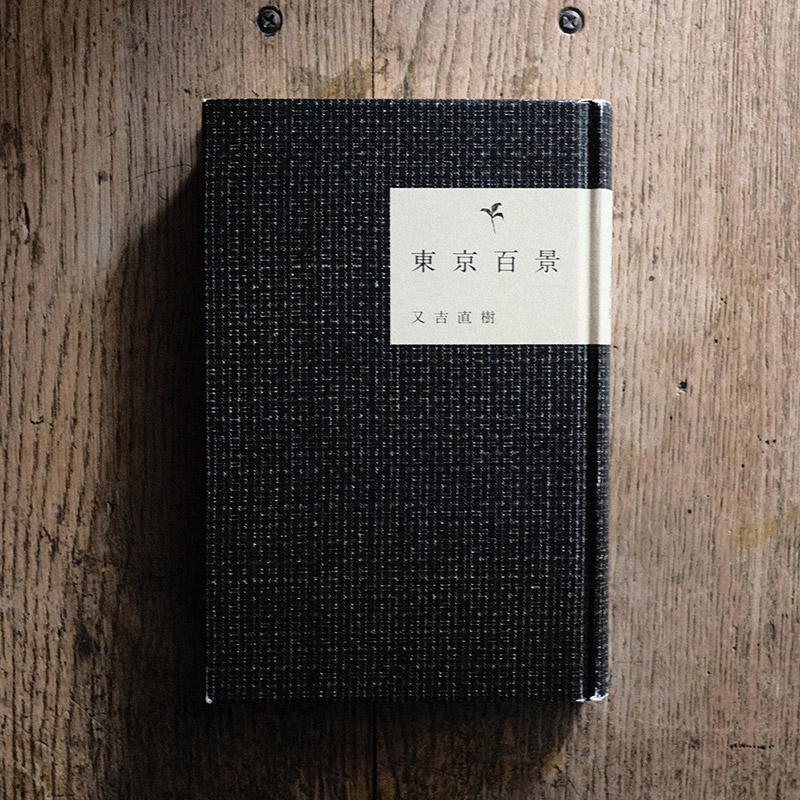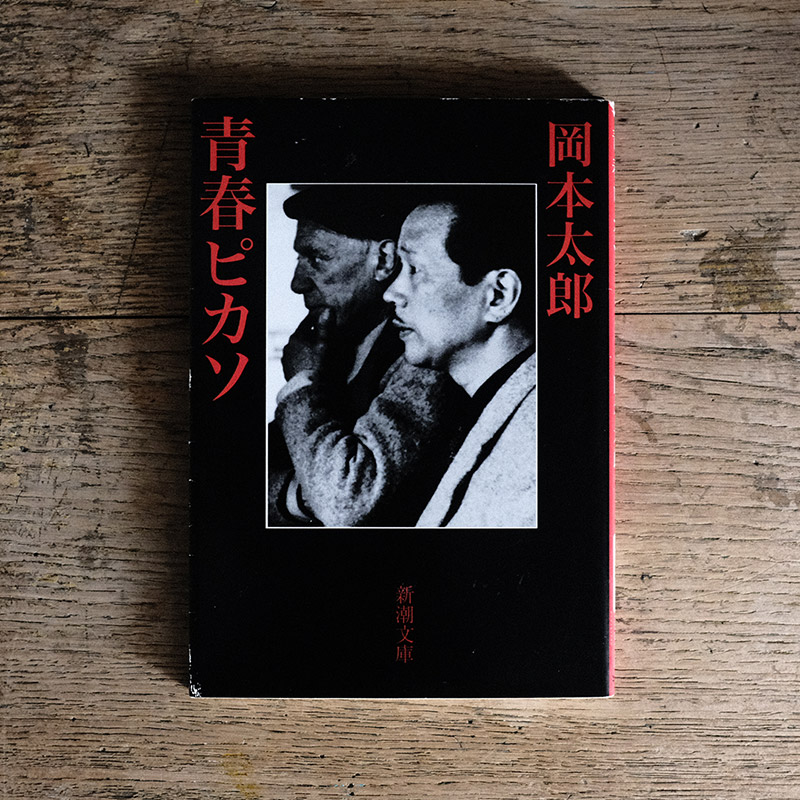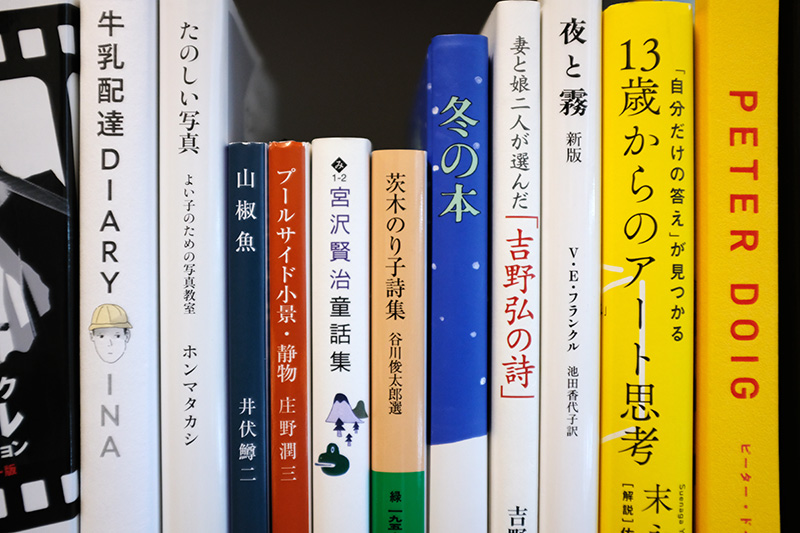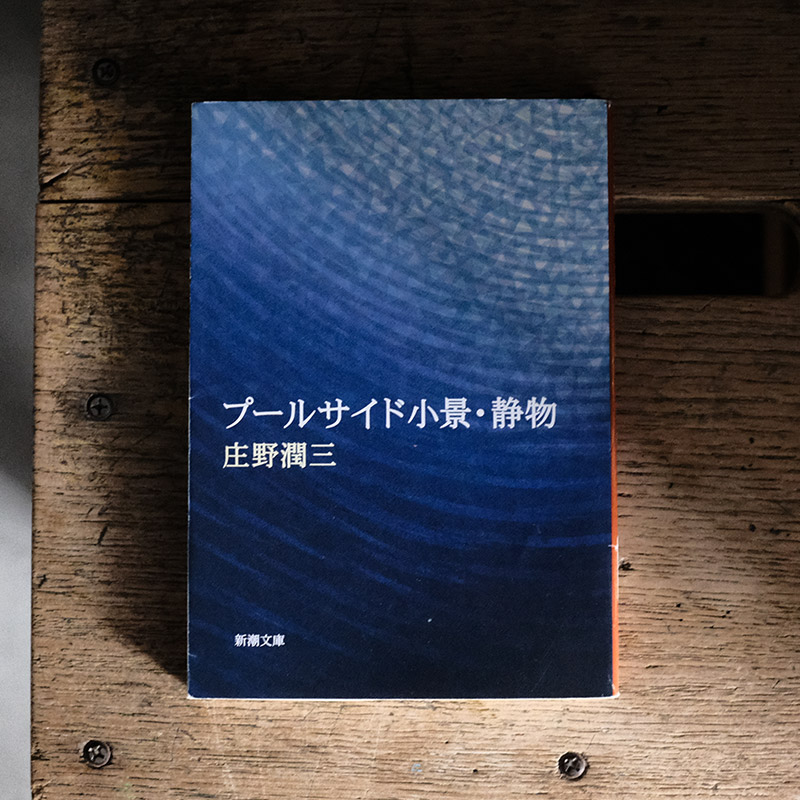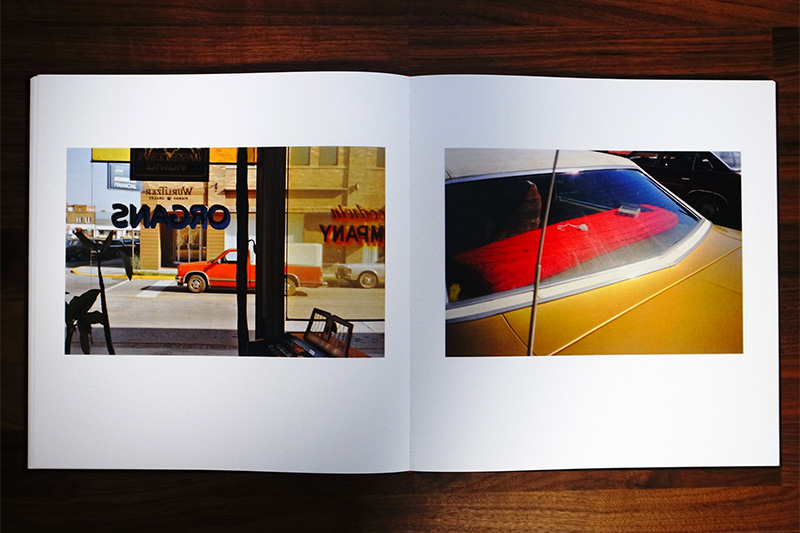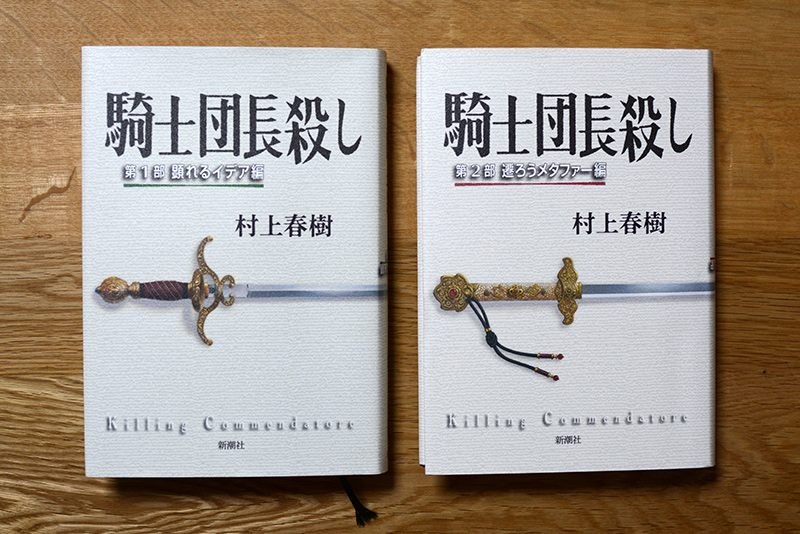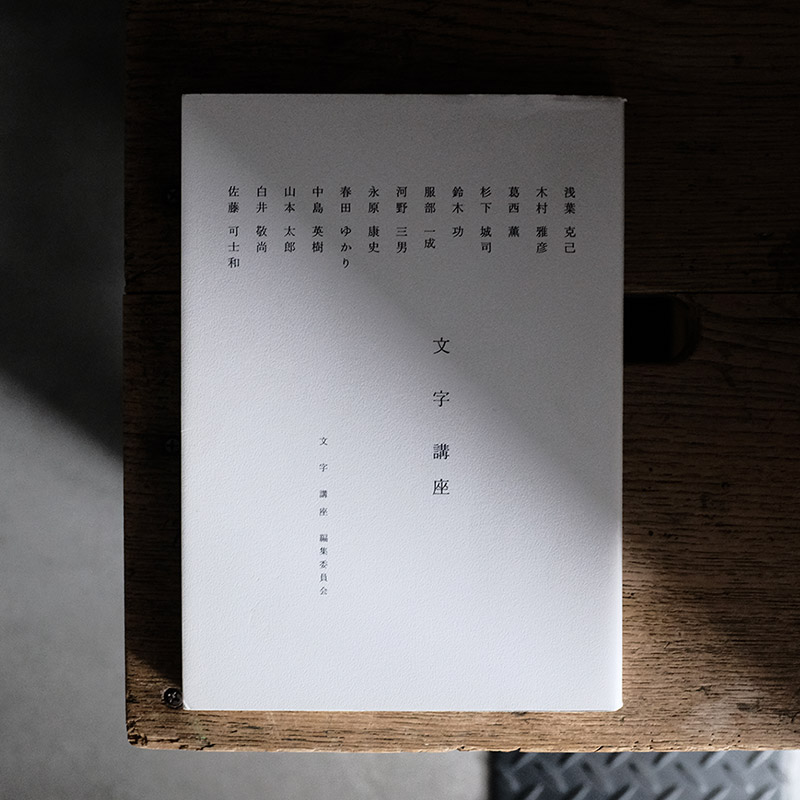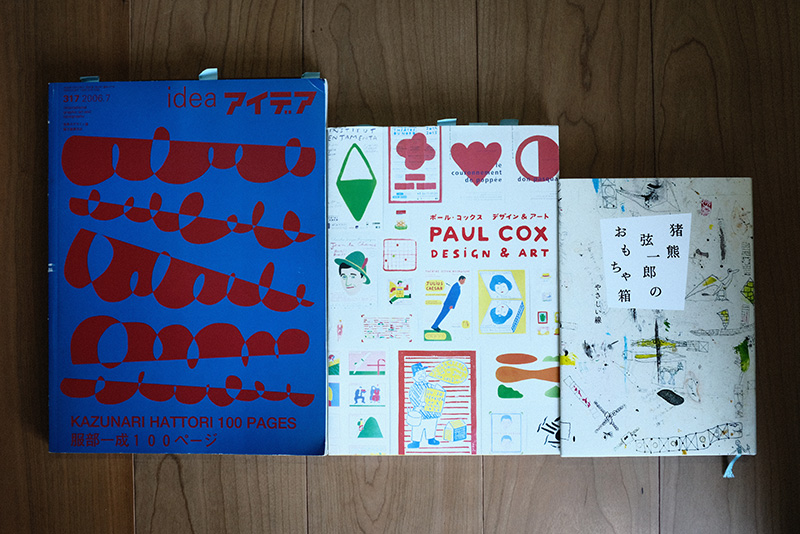
今年買ったデザイン本の中では、
この3冊が印象に残っています。
『ポール・コックス デザイン&アート』は
ちょいちょい本棚から
引っ張り出してきて眺めてます。
ぼくは他人のアトリエ写真を見るのが好きで
無数のデザイン本を
無造作に積み上げている
ポールさんのアトリエに憧れます。
『服部一成100ページ』は
ずっと探していてようやく手に入れました。
服部さんが手掛けた多様な
広告・グラフィックが載っていて最高です。
ぼくはデザイナーの中では
服部一成さんが好きなのです。
キューピーマヨネーズの広告の
ラフな手描き文字に影響を受けました。
服部さんの考え方にも
ぼくは影響を受けていて
『文字講座』という本に書かれた
服部さんの言葉にはシビれました。
「デザインは手段にすぎないんだけれども、
しかし手段を超えたなにかがなければ
デザインは輝かない。
意味を伝えるために存在していながら、
意味を超えて輝くことを、
だれもが無意識に期待している」
(文字講座 115Pより)