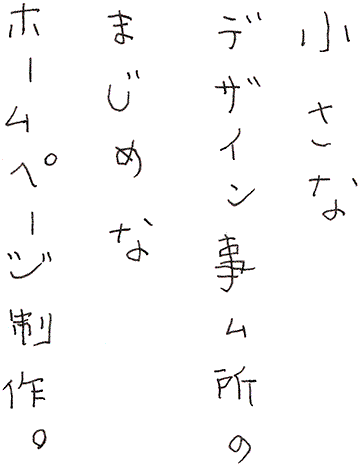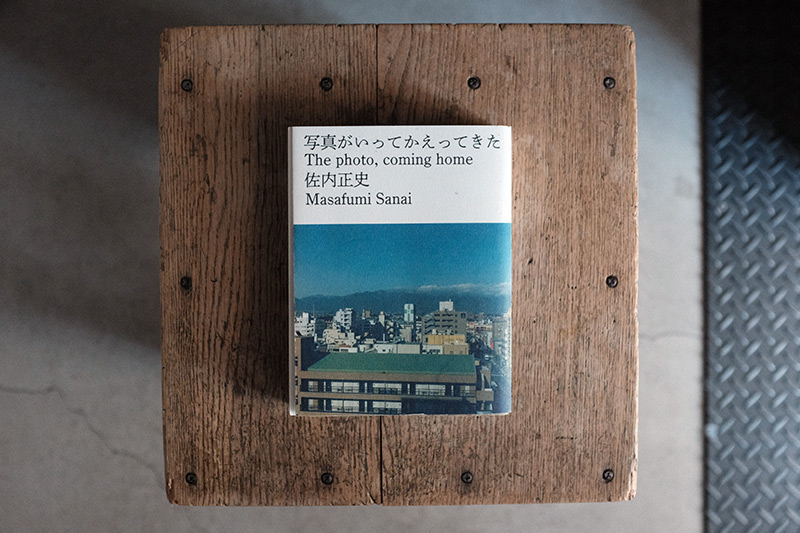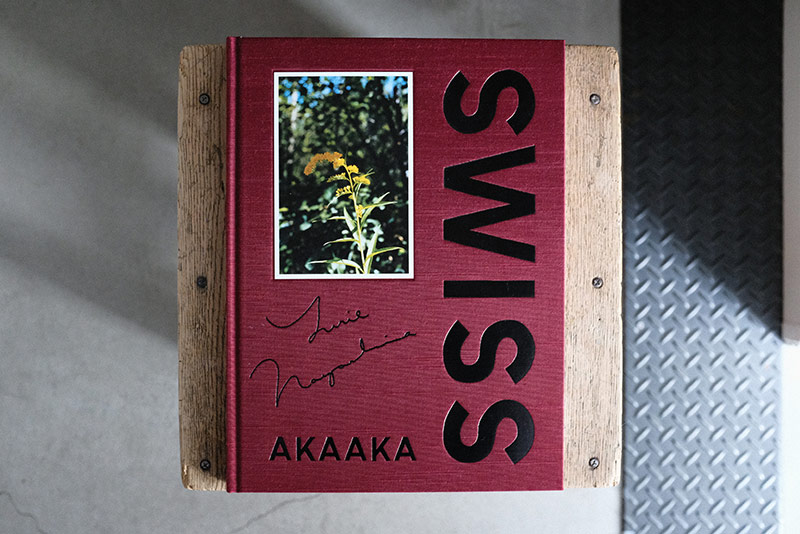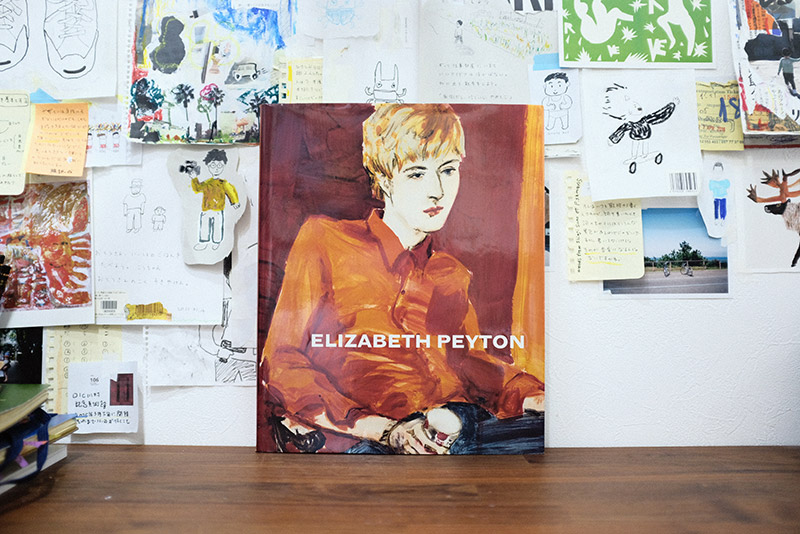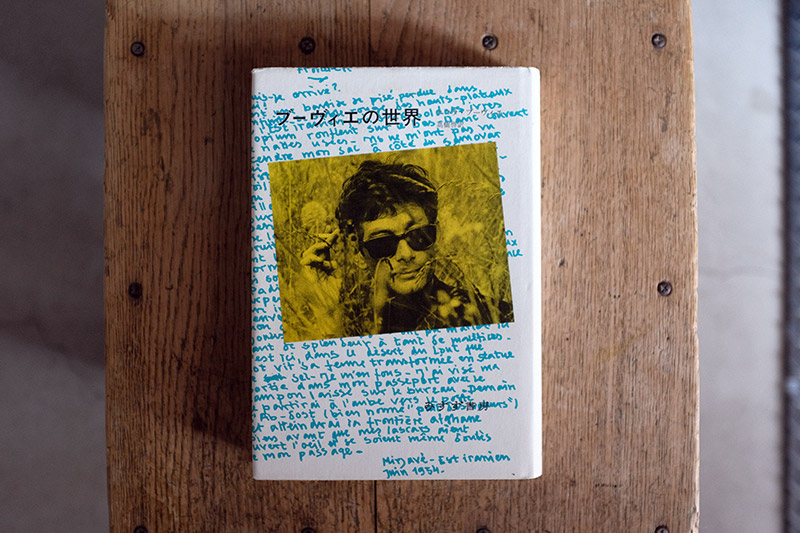残り160ページ。ゴールが見えてきた嬉しさと、終わってしまう寂しさ、後者のほうが大きいです。いま、ハンス・カストルプがレコードにハマっています。とても重くて、劇的なエピソードのあとで、しかも長い長い物語の最終盤にきて、主人公がレコードにハマるという意外性。クラシックを中心に、音楽の話題が展開されています。まさかこのまま終わらんよね?小説の中で音楽のうんちくを語るといえば、村上春樹さんがその代表ですが、きっと村上さんは魔の山の影響を受けていたんだな。ノルウェイの森の主人公(ワタナベくん)は、たしか魔の山を読んでいましたよね。